【相続する方へ】被相続人ができる相続対策について
~相続に関わる方々が健康かつ
存命中の相続対策が重要~

被相続人(相続させる亡くなった方)が亡くなった後にできる相続対策はごくわずかです。家族にかかる相続の負担を減らし、相続人同士で揉める「争族」を避けるためには、被相続人が健康かつ存命中に対策を打つ必要があります。具体的な対処方法をチェックしてみましょう。
大切な家族の負担や争いを避けるためにできること
被相続人が死後にできる相続対策はごくわずかです。そのため、相続対策の大半が被相続人の生前中に行うものになります。また、被相続人が健康かどうかも重要なポイントです。存命だとしても、認知症などを発症して判断能力がないとみなされると、遺言書の作成などができなくなります。そのため、相続対策は1日でも早く始めることが大切といえます。
被相続人が今すぐできる「4つの生前対策」の中身
被相続人が今すぐに始められる生前対策の種類は、大きく4つです。具体的な生前対策の中身について解説します。
point01
財産の内容を把握する
生前対策の第一歩は財産の把握です。遺産分割協議の対象となる財産が、どこにどれだけあるのかを確認しましょう。財産の主な種類は以下のとおりです。
 不動産
不動産
(土地、家屋 ) お金
お金
(現金、預金 ) 動産
動産
(自動車、宝石、
機器、骨董品 ) 有価証券
有価証券
(株式、社債、投資信託 )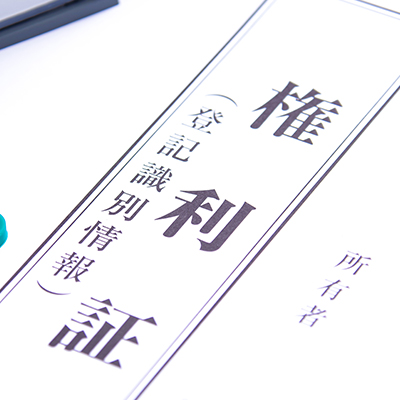 権利証
権利証
(借地権、借家権 )
生前に財産の内容を把握しておくと、相続人のうち誰がどの財産を引き継ぐのかを整理しやすくなるほか、相続税も計算しやすくなります。
財産の内容を把握しないまま相続が発生すると、相続人は「相続財産調査」を行わなければなりません。相続財産調査には1ヶ月~2ヶ月程度の期間がかかり、数万円~数十万円の調査費用も発生します。財産の見落としを防ぐためにも、できるだけ早く財産の内容を把握しておきましょう。
point02
不動産などを生前贈与する

生前贈与とは、被相続人の存命中に、特定の人物へ財産を贈ることです。生前贈与しておくと、将来的に相続が発生した際の財産を減らせます。そのため、家族に重くのしかかる相続税を軽減できる可能性があることが生前贈与のメリットです。
特に不動産は「誰がどの割合を取得するか」をめぐってトラブルになりやすい財産です。生前贈与なら、被相続人が希望する人物に対して、確実に不動産を引き継げます。また、贈与時期を自由に選択できるため、評価額が下がったタイミングで生前贈与をすると、節税効果がさらに高まるでしょう。
生前贈与の注意点は、贈与された人物に贈与税が課税されることです。ただし、1年間で1人につき110万円までの贈与は非課税となり、相続税を支払うよりもお得になる可能性があります。生前贈与を効率的に利用するためには、多くの相続人に生前贈与を行い、非課税枠を多く活用しましょう。
point03
遺言書を作成する
遺言書とは、被相続人が亡くなった後の遺産配分について、生前に決めるために残す書類です。遺言書を作成しておくと、被相続人の意思を相続人に対して明確に伝えられます。有効な内容の遺言書があれば、相続人は遺産分割協議を行う必要がありません。遺言書の種類と特徴は以下の3つです。
| 自筆証書遺言 | 遺言書の全文を被相続人自身が自筆で記入・捺印する |
|---|---|
| 公正証書遺言 | 公証役場において公証人の監督を受けながら記入・捺印する |
| 秘密証書遺言 | 自分で遺言書を作成し封をしたうえで公証役場に預ける |
どの種類を選ぶか迷った場合や、確実に効力を発揮する遺言書を用意したい場合は、公正証書遺言を作成しましょう。作成時には手数料がかかりますが、確実に有効な遺言書を作成できます。その他の方法で遺言書を作成する場合、内容に不備が認められると無効になるため注意しましょう。その場合、相続人同士が遺産分割協議を行うため、被相続人の意思どおりに相続が行われるとは限りません。
point04
万一に備えて家族信託を行う

家族信託とは、被相続人が認知症などを発症し、正常な判断能力を失った場合に備えられる制度です。家族信託を行うと、財産を管理する権利を家族や親族に託せます。被相続人が病気や事故などにより財産の処遇についての意思を示せなくなったとしても、受託者が被相続人に代わって財産の管理・処分を行えることが特徴です。
家族信託のメリットをご紹介します。
成年後見制度よりも柔軟に財産管理ができる
家族信託とよく似た「成年後見制度」では、資産の積極活用や生前贈与といった相続税対策ができません。家族信託の場合、不動産売却や買い替えなども受託者の判断と責任のもとで行えるため、柔軟な資産管理が可能です。
共有によるトラブルを避けられる
複数の相続人が不動産を相続して共有すると、共有者全員の合意がなければ不動産売却などの処分行為ができません。しかし、家族信託は特定の受託者に不動産を管理・処分する権限を集約できるため、共有によるトラブルを予防しやすくなります。
【相続を受ける方へ】相続人ができる相続対策について
~事前確認を怠らずに行うと
スムーズに相続できる~

相続対策というと「被相続人が準備すること」といった印象を持つ方が多いかもしれません。しかし、相続人(相続を受ける方)ができる相続対策もあります。相続人ができる相続対策で重要なのは、事前準備を怠たらずに行うことや、状況別に最適な対処法を把握しておくことです。この2つのポイントを押さえておくと、急に相続が発生したとしても、スムーズに理想どおりの相続が可能になります。
不動産相続の前後に
相続人がやっておくとよいこと
不動産相続ではさまざまなトラブルが発生しており、相続人同士が争う「争族」に発展するケースも珍しくありません。そのようなトラブルを回避するために、相続人がやっておくとよいことを確認しましょう。
「相続前」にできる相続対策・節税対策
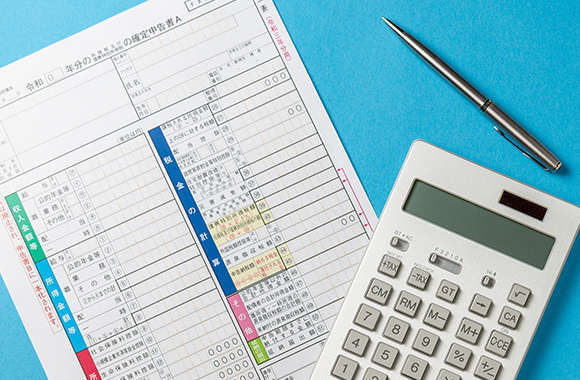
相続前にできる、相続人側の相続対策と節税対策が2つあります。それぞれの対策を実施することにより、不動産相続のトラブルを避けやすくなるため、有効な対策を把握しておきましょう。
任意後見制度を活用する
任意後見制度とは、特定の相続人を任意後見人として選任し、不動産売却などを主導する権利を与える制度です。親などの被相続人が事故や病気などにより正常な判断能力を失うと、相続人の一存では不動産売却などの処分行為を行えません。しかし、事前に任意後見人を選任しておくと、任意後見制度により不動産売却が可能になります。
任意後見制度は、被相続人の住所を管轄する家庭裁判所で、公証人が作成する公正証書を利用して締結します。必要な費用については、状況により変わってまいりますので、一度当社へご相談ください。
相続税対策を行う
預貯金や有価証券、不動産といった高額な財産を取得する場合は、相続税が発生する可能性があります。相続税は以下の方法により節税が可能です。
- 事前に生前贈与を行う
- 生命保険の非課税枠を利用する
- 土地の相続税評価額を下げる
贈与税が非課税になる範囲内で事前に生前贈与を行うと、相続時に課税される財産を減らせるため、節税対策につながります。詳しくは「不動産などを生前贈与する」 もご確認ください。
生命保険の非課税枠を利用したり、土地や建物の相続税評価額を引き下げたりすることも有効な節税対策です。たとえば、アパートの建築などを行うと土地の相続税評価額が下がる可能性があり、節税対策につながります。
「実家の相続後」に必要な手続きについて

実家を相続した場合は名義変更の手続き(相続登記)が必須です。相続登記は令和6年4月に義務化され、相続の発生を知った日から3年以内に完了させる必要があります。(法務局:相続登記が義務化されました)
また、相続税が発生する場合は、相続の発生から10ヶ月以内に申告しなければなりません。相続税には基礎控除を適用でき、控除を越えなければ相続税が発生しないため、まずは実家の相続により相続税がかかるかどうかを確認しましょう。
相続税の基礎控除について
相続税の基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の人数です。仮に法定相続人が3人いる場合、合計4,800万円を基礎控除できます。詳しい計算方法は国税庁の「相続税のあらまし」 または「相続税の申告要否判定コーナー」 に掲載されているため、注意点も含めて確認しておきましょう。
相続人が同居していた実家は特例により評価額が引き下げられる
相続する実家に相続人が同居していた場合などには「小規模宅地等の特例」 を適用できます。これにより、330平米までの土地の相続税評価額が80%減額されるため、大幅な節税が可能です。
土地の相続税評価額は路線価方式または倍率方式で評価され、目安は市場で売買されている金額の80%程度です。建物の相続税評価額は、固定資産税評価額の金額をそのまま利用します。固定資産税評価額は、管轄する市町村から送付される「固定資産税の課税明細書」から確認しましょう。
相続した実家に住まない場合の処分方法・節税方法

相続した実家に住まず空き家にすると、劣化が進んで資産価値が急落したり、固定資産税などの維持費が無駄に発生したりします。そのため、空き家のまま放置することはおすすめできません。実家を処分する方法は「売却」「貸し出す」「土地活用をする」の3つです。
売却する場合は「相続空き家の特例」を利用できる、相続から3年以内に売却しましょう。所定の条件を満たす場合、売却益のうち3,000万円までが控除されるため、譲渡所得税を節税できます。(国税庁:被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例)
Pick UP
不動産の相続対策は専門家が在籍する当社にお任せください

不動産の相続対策が必要な場合は、しみず不動産にお任せください。税理士や司法書士と連携し、不動産相続の専門家として被相続人様・相続人様をサポートできます。
また、行政書士、司法書士、弁護士、税理士と提携していることも当社の強みです。当社にご相談いただければ不動産の売却から法的手続きについてのサポートまでご対応いたします。ご実家に荷物(残置物)を残したままでも不動産を手放していただけます。まずはお気軽に当社までお問い合わせ ください。


